
当ウェブサイトは、サービス向上の目的のためCookieを利用しています。
Cookieの利用に同意していただける場合は、同意ボタンをクリックしてください。
閲覧を続ける場合には、同意していただいたものといたします。
地震と住宅の新常識

災害に備える家づくりの知識を深める:構造躯体の役割と重要性を解説のインデックス
相次ぐ地震や台風といった自然災害の影響で、災害に備える家づくりへの関心が高まっています。災害に耐えるために強固な構造躯体を重視する一方で、具体的にどのような部分に注意すればよいのか、疑問に感じることもあるでしょう。
災害に備える家づくりを進めたい方のために、今回は構造躯体とは何かをはじめ、耐震性に関わる構造躯体の種類について詳しく解説します。
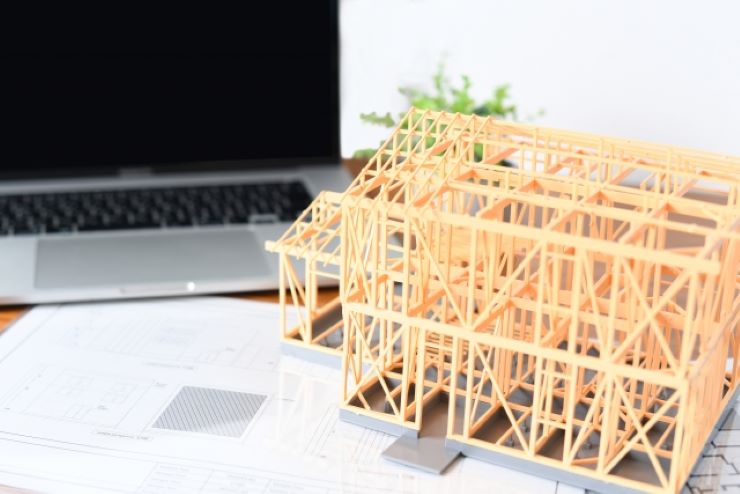
といった骨組みを指すことが多く、建物の耐震性や強度に関わる重要な部分です。構造躯体は、地震や台風といった自然災害の発生時も外壁や屋根を強固に支え、建物を守る役割があります。
建物の骨組みである構造躯体に含まれるのは、主に次の6つです。
・基礎
・柱
・梁
・壁
・床
・斜材
それぞれが持つ役割とともに、特徴を詳しく見ていきましょう。
基礎とは建物の土台となる部分のことで、建物の傾きや地盤への沈み込みを防ぐ役目を担っています。一般的な戸建住宅でよく使われているのは、「布基礎」と「ベタ基礎」の2種類です。
横から見て逆T字型に見える基礎を埋め込み、柱を建てて「点」で建物を支える布基礎に対し、ベタ基礎はコンクリートを流し込んで基礎を作り、建物を「平面」で支えるのが特徴的。面で支えるベタ基礎は耐震性や防湿性に優れている一方で、布基礎はベタ基礎よりも材料が少なくて済むため、建築コストを抑えられるのもポイントです。
関連記事:住宅の基礎の重要性を知ろう|基礎の種類やそれぞれの特徴・工事手順を解説
柱とは、地面に対して垂直に立てる部材のことです。屋根や床、人、家具などの重みを受け止め、土台や基礎へと伝えます。また、地震や風による水平方向の力に抵抗するのも役割です。
梁とは、柱と組み合わせて地面と水平に掛ける部材のこと。屋根や床の重みを支え、直下の柱に伝えるのが重要な役割です。また、地震による揺れや台風発生時などの強い風圧から建物を守り、変形を抑えています。
壁は、地震や風などの水平方向の力に抵抗するために重要な構造体です。特に壁式工法や木造軸組工法において、体力壁は構造躯体の強さを保つ要となるため、ある程度間取りに制限が出る場合もあるでしょう。一方、ラーメン構造では柱や梁が建物の重みを支える部分として重要視されるため、壁の少ない大空間の間取りも作りやすくなります。
床には、人や家具などの重みを柱や梁に伝える役割があります。また、耐震性を確保するためには柱と梁でできたフレームや耐力壁の強さが重要ですが、床の強さも重要です。柱や壁、耐力壁と繋がっている床が弱いと、床の変形が大きくなりすぎたり壊れてしまったりして、力がうまく伝わりません。
斜材は「シャザイ」と読み、構造の角と角を斜めにつなぐように入れて、強度を補強する部材のこと。木造建築では「筋交い(すじかい)」と呼ばれることもあり、地震発生時に建物にかかる水平方向の力に耐えるために柱と柱の間に入れられます。
斜材は建物の耐久性を高める役目があるため、構造によっては、耐久性を保つためにある程度の壁が不可欠です。構造によっては、仕切りの少ない開放的な間取りや一続きになった大空間に、制限が出やすい点に注意しましょう。
構造躯体は、使用する素材によって3種類に分けられ、それぞれの特徴や耐震性も異なります。災害に備える家づくりを進めるなら、構造躯体の種類ごとの違いも正しく把握しておきましょう。それぞれの特徴について、詳しく解説します。
関連記事:家の構造は何を選ぶべきなのか?木造・鉄骨造・RC造の特徴を比較
木造は基礎部分を除く構造躯体に木材を利用した建て方で、柱や梁・床・壁・斜材など多くの部材を組み合わせて作られるのが特徴です。中でも柱や梁を組み合わせ、先に屋根を作る「木造軸組工法」は雨の多い日本の気候風土に適しています。
他の鉄骨造やRC造と比べると、木造の耐震性は劣ると感じられますが、決して木造の耐震性が低いわけではありません。木は他の構造で使われている鋼鉄やコンクリートと比べて軽いため、自重によって倒壊しにくいのが特徴です。
関連記事:木造住宅のデメリットとは?後悔しない家づくりのために知っておきたいこと
鉄骨造は柱や梁に鉄骨を用いたもので、Steel(鋼)の頭文字をとってS造とも呼ばれる構造です。厚さ6mm以上の鉄骨を用いたものは重量鉄骨と呼ばれ、高層ビルやマンションといった大型の物件でよく使われます。一方アパートや戸建住宅は、厚さ6mm未満の軽量鉄骨を使うのが一般的です。
鉄は引っ張る力に強く、力が加わるとしなる性質を持っているため、地震のエネルギーを吸収して建物への影響を抑えます。鉄骨は丈夫な鋼製ですので、耐震性だけでなく耐久性にも優れていますが、木造と比べると素材そのものの価格が高く、建築コストもかかりやすい点に注意が必要です。
RC造とは、鉄筋で作られた枠組みの中にコンクリートを流し込んで作る構造のこと。引っ張る力に強い鉄筋と、押し込んでくる力に強いコンクリートのどちらの長所も備えています。耐久性と耐震性に優れており、開口部を広くできるのも魅力です。しかし、素材が重く建築コストもかかるため、中低層のマンションや施設などで比較的よく使われています。

木造建築に鉄骨造やRC造でよく使われるラーメン構造を取り入れたSE構法は、木造の良さに鉄骨造やRC造の持つ躯体の強さを組み合わせた構造躯体です。SE構法が持つ、構造躯体としての強さの秘訣を見ていきましょう。
SE構法では、一棟一棟で徹底した構造計算(許容応力度計算)を行っています。構造計算とは、厳密に測定した科学的な根拠をもとに、建物の安全性を確認するために実施する計算のこと。地震や台風などの災害時に建物にかかる水平力や、建物そのものの重さも関わる鉛直荷重について、構造躯体の柱や梁が十分に耐えられるかを1つ1つの部材で検証しています。
建物の安全性を一目でわかる数値として実証する構造計算ですが、一般的な木造住宅において、構造計算の実施は法律で義務付けられていません。SE構法は通常鉄骨造やRC造で行われている緻密な「許容応力度計算」を全棟で実施し、住まいの安全性を科学的な根拠による確かな数値で示しています。
SE構法で用いているのは、耐久性の優れた構造用集成材。木材には自然のままの木を切り出した状態の無垢材と、一定の大きさに加工した木材を貼り合わせた集成材があり、建物のどの部分に使用するかによって選ぶ木材も変わります。
天然の木目が楽しめる無垢材は、床材としてフローリングに使われることも多く、耐久性に優れた集成材は構造躯体に最適です。SE構法は加工の過程で木材を選別し、一定の強度が担保できる木材のみで構造用集成材を製造。製造過程から強度を確保できる集成材ならではの安心感で、住まいの強度を高めます。
従来の木造建築では伝統的な木造軸組工法が多く用いられ、梁と柱の接合部分は釘や「ほぞ」と呼ばれる穴加工によって接合するのが一般的。しかしこの方法は地震などで強い力がかかったときに接合部に大きな負荷がかかるため、柱や梁が欠損するリスクに注意しなくてはなりません。
木造ならではの軽量さと設計しやすさに強度を加えるため、SE構法では接合部分に独自のSE金物を採用。木造建築の良さと金物の強さを掛け合わせることで、災害に強い家づくりを実現します。

SE構法の優れた構造躯体が実現する、家づくりにおける3つの強みを見ていきましょう。
SE構法が採用しているのは、鉄骨造やRC造で主に使われているラーメン構造。柱と梁を接合させて作る枠組みで建物を強固に支えます。
独自開発したSE金物を取り入れた構造の工夫で、木造住宅でありながら鉄骨造やRC造と遜色ない耐震性を実現。戸建住宅以外に店舗や倉庫、ビルといった大規模な建物もSE構法の採用で木造が可能になり、木造ならではの自然素材の良さが感じられる建築物も増えています。
木造住宅でよく採用されている木造軸組工法(在来工法)では、柱と梁を支えるために斜めに筋交いを入れる必要があり、広い開口部の実現が難しくなっていました。ラーメン工法を採用するSE構法は、筋交いが不要で開口部を広くとれるのが魅力です。
横方向だけでなく、縦方向の開放感も高められるので、吹き抜けを採用した明るいリビングなど注文住宅への夢も広がります。SE構法なら設計の自由度の高さを活かし、理想を叶える家づくりが可能です。
耐震性に優れ、構造計算の実施や構造用集成材の使用など構造躯体の強さにこだわったSE構法は、資産価値を長く保つ家づくりを叶えます。
一般的に木造住宅は資産価値を保つのが難しく、耐用年数は約30年間ともいわれてきました。しかし、これはあくまで耐用年数の目安であり、構造や建て方へのこだわりや住んだ後の適切なメンテナンスによっても、住まいの耐用年数は変わります。
住まいの骨組みとなる構造躯体にこだわったSE構法なら、住まいの耐用年数を長く保ち、資産価値を維持しながら安心して住み続けられる家づくりが可能です。
自然災害の発生は、現代の技術を結集しても予想が難しく、いつ起きるとも限らないため日頃からの備えが欠かせません。地震や台風などの災害から大切な家族と住まいを守るためにも、構造躯体の強さにこだわった家づくりを進めましょう。
耐震性の高いラーメン構造を採用し、構造や素材への工夫の成果を構造計算で実証するSE構法は、長く安心して住み続けられる理想の住まいを実現します。SE構法での家づくりが気になる方は、ぜひお近くの認定工務店へお気軽にお問い合わせください。
SE構法は、木造住宅の構造技術です。丈夫な材料とラーメン構法による強い構造躯体と、一棟一棟に対する基礎から上部までの厳密な構造計算を行う点が最大の特長です。私たちの特長を是非ご覧ください。
株式会社エヌ・シー・エヌが開発した構法で、集成材とSE金物による堅牢な構造媒体を持ちすべての建造物に対してひとつひとつ構造計算(許容応力度等計算)を行うことで、
を同時に実現できる構法です。
(施工は全国の登録工務店でしか行うことができません。)

