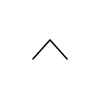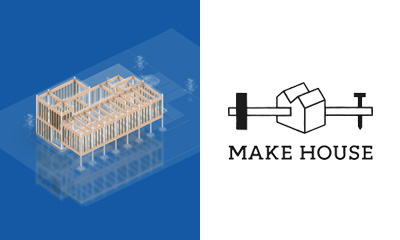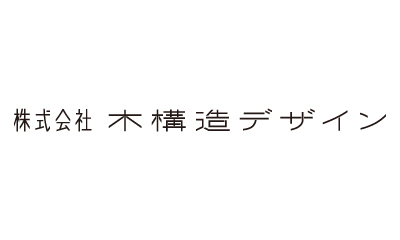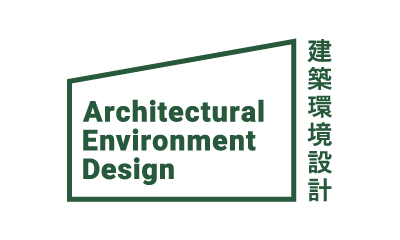【青森県】中大規模木造の実務ポイントとSE構法の技術
青森県の非住宅用途の木造建築は、豊富な県産材の活用とカーボンニュートラルへの関心の高まりに支えられ、近年着実に増加しています。
具体的には、公民館や学校、保育園・幼稚園、観光施設、商業ビルなどで木造や木質内装が採用される事例が多く見られます。
地元産のヒバやスギなどは調湿性や断熱性に優れ、快適な空間を演出するとともに、県内経済の活性化や林業との連携強化にもつながります。
また、耐震設計の進歩やCLT(直交集成板)の実用化など、大規模建築での木造化を後押しする技術革新が進んでいることも大きな要因です。
さらに、青森県では公共施設への県産材導入を奨励する政策が推進されており、官民が協力して設計・施工の技術レベルを高める取り組みが活発化しています。
観光振興を目的とした道の駅や文化施設においても、地元の木をふんだんに使用した建築が誕生し、訪問者に青森の森林資源の豊かさや木造建築の魅力をアピールする場となっています。
今後も、地元産材のブランド化やサステナブル建築に対する需要の高まりを背景に、非住宅分野での木造化がさらに拡大していくことが期待されます。
この記事では青森県における中大規模木造の実務ポイントとSE構法の技術についてお伝えします。
<このコラムでわかること>
・中大規模木造の普及が進む青森県の特徴
・青森県の青い森県産材利用推進プラン
・青森県における公共建築物等の木材利用
・青森県の中大規模木造に最適なSE構法の概要
・SE構法へのお問合せ、ご相談について
・まとめ
中大規模木造の普及が進む青森県の特徴

青森県は本州最北端に位置し、冬季の厳しい寒さや豪雪に加えて海洋からの強風にもさらされるため、その気候特性が住宅・建築文化に大きく影響を与えています。
県内は日本海側の津軽地方と太平洋側の下北・三八上北地方、さらには内陸部を含む複数の地域に分かれ、それぞれが異なる気候条件を持つことから、多様な建築様式が発達してきました。
特に津軽地方は日本海からの湿った風が冬季の豪雪をもたらすため、積雪量が多く、屋根の形状を急勾配にして雪を滑り落としやすくしたり、柱や梁などの構造体を強化して雪の重みに耐えられるようにするなど、独自の工夫が見られます。
また、青森県は風雪だけでなく、夏場の高温多湿にも対応する必要があります。
冬の厳しい寒さに備えて断熱材を十分に入れるだけでなく、夏には熱気を逃がしやすくするため、窓や開口部の配置にも注意が払われます。
特に沿岸部や台風の影響を受けやすい地域では、強風対策として屋根材や外壁材の固定を強化するほか、風除室や雪囲いを設けて屋外からの冷気や風雨を遮断する工夫も一般的です。
加えて、青森県は林業が盛んで、ヒバをはじめとする豊富な森林資源を有しています。
地元産の木材を利用した木造住宅は、湿度調整や保温性、香りによるリラックス効果などの点で評価が高く、伝統的な木組みの技法を活かす事例も数多く見られます。
一方で、近年は耐震性能や省エネルギー性能への関心が高まり、耐震補強や複層ガラスの導入、高性能断熱材の活用など、現代技術を融合した住宅づくりが進められています。
さらに、青森県内では広大な農地や果樹園と隣接する形で住まいが建つケースも多く、地域の産業や景観との調和が図られた建築設計が重視される傾向にあります。
例えば、りんご畑の保護や管理作業の利便性を考慮し、農作業用の倉庫や作業場を兼ね備えた住宅が設計されることも珍しくありません。
周囲の自然環境と共存する観点から、屋根の色や外壁材を景観に溶け込むものに選択するなど、デザイン面での配慮も行われています。
こうした多彩な気候・風土条件を背景に、青森県の住宅・建築文化は防寒・防雪・防風といった要素を重視した伝統的な知恵と、地場産木材や最新の建築技術を取り入れた持続可能な暮らしの実現を目指す取り組みが融合しています。
今後も、自然環境や地域産業との調和を図りつつ、快適かつ堅牢な住環境づくりが一層推進されていくでしょう。
青森県の青い森県産材利用推進プラン

青森県の「青い森県産材利用推進プラン」は、当初「公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律」に基づき、公共建築物等における県産材の利用の促進のための施策について定められました。
その後、この法律が「脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律」に改正され、国が木材利用に関する基本方針を策定したことを受け、青森県の方針について変更が行われました。
青森県の「青い森県産材利用推進プラン」のポイントは主に下記です。
青森県の森林資源利用計画では、豊富な森林資源を活かした地域経済の活性化や、環境保全と持続可能な利用の両立を目指す方針が示されています。
木造建築に取り組む建築実務者にとって重要なポイントとしては、まず「県産材の利用促進」が挙げられます。
青森ヒバやスギなど、県産材の強度や耐久性、抗菌・防腐性能などを活かしながら、地産地消を推進することで物流コストの削減や地域経済への貢献が期待できます。
加えて、地元の製材所や木材加工業者との協力体制を構築することで、必要な材質や寸法の安定供給が可能となり、より柔軟な設計・施工が行いやすくなるでしょう。
次に、計画には森林の循環利用を図るための「適正な森林施業」や「持続的な森林管理」の重要性が明記されています。
これは、建築実務者が木材を安定して入手し続けるためにも不可欠です。
適切な森林保全や育林が行われることで、材質の良い木材が持続的に供給されるだけでなく、CO₂の吸収や水源涵養といった森林の公益的機能の維持にもつながります。
また、計画では木材の利用拡大による「カーボン・オフセット効果」にも言及されており、木造建築の増加が温室効果ガス削減に寄与する点が強調されています。
これはSDGsへの対応を進める建築業界にとって大きなアピールポイントとなるでしょう。
さらに、県産材を活用した公共建築や大型木造施設の普及を後押しするため、行政や各種団体との連携が推奨されています。
具体的には、公共施設の木造化や内装への県産材の積極導入のほか、木材利用技術の高度化に向けた研究開発や、設計・施工分野での人材育成などが挙げられます。
こうした取組は建築実務者にとって、新たな設計手法の開発や高付加価値の提案につながる可能性が高いでしょう。
県内外への情報発信による需要拡大策も含まれています。
建築実務者が青森県産材の特徴や実績を積極的にPRすることで、施主や消費者の理解を得やすくなり、ひいては需要拡大やブランド力向上につながります。
これらの施策を総合的に進めることで、森林資源の持続的利用と地域経済の発展を両立することが、同計画の大きな狙いとなっています。
木造建築に携わる方々にとっては、地元資源の強みを最大限に活かし、環境負荷の低減や地域振興にも寄与できる絶好の機会と言えるでしょう。
青森県における公共建築物等の木材利用

公共建築物は、広く国民一般の利用に供するものであることから、木材を用いることにより、木と触れ合い、木の良さを実感する機会を幅広く提供することができます。
このため、建築物木材利用促進基本方針では、公共建築物について、積極的に木造化を促進することとしています。
林野庁の資料「森林・林業白書」によると、青森県では下記のように木造率が推移しています。
・2017年度:
建築物全体(61.2%)、公共建築物(26.4%)、うち低層の公共建築物(44.5%)
・2019年度:
建築物全体(65.5%)、公共建築物(23.4%)、うち低層の公共建築物(36.6%)
・2021年度:
建築物全体(65.8%)、公共建築物(23.1%)、うち低層の公共建築物(36.1%)
2022年度以降に整備に着手する国の公共建築物については、建築物木材利用促進基本方針に基づき、計画時点においてコストや技術の面で木造化が困難であるものを除き、原則として全て木造化を図ることになっています。
青森県の中大規模木造に最適なSE構法の概要

耐震構法SE構法(以下、SE構法)は、大規模木造建築物の技術を基に開発された技術です。
SE構法は構造計算された耐震性の高い木造建築を実現する、独自の建築システムです。
SE構法は耐震性の高さ、設計の自由度、コストパフォーマンスの良さ、ワンストップサービス等で高い評価を受けており、さまざまな大規模木造の実績が増えています。
SE構法は、単純に「剛性のある木質フレーム」というだけではなく、さまざまな利点を追求し、大規模木造で求められる大空間・大開口を可能にして、意匠設計者の創造性を活かせる設計の自由度を提供しています。
関連記事:耐震構法SE構法は全棟で立体解析による構造計算を実施
SE構法は「木造の構造設計」と「構造躯体材料のプレカット」そして施工というプロセスを合理化することでワンストップサービスとして実現した木造の工法です。その合理的なシステムが、設計・施工のプロセスにおいて納期や工期の短縮につながります。
関連記事:「ウッドショック等のリスクにSE構法のワンストップサービスが強い理由」
SE構法へのお問合せ、ご相談について

大規模木造をSE構法で実現するための流れは下記となります。
1.構造設計
SE構法を活用した構造提案を行います。企画段階の無料の構造提案・見積りから、実施設計での伏図・計算書作成、確認申請の指摘対応等を行っております。また、BIMにも対応可能です。
2.概算見積り
SE構法は構造設計と同時に積算・見積りが可能です。そのため躯体費用をリアルタイムで確認可能で、大規模木造の設計において気になる躯体予算を押さえつつ設計を進めることが可能です。
3.調達
物件規模、用途、使用材料を適切に判断して、条件に応じた最短納期で現場にお届けします。また、地域産材の手配にも対応しております。
4.加工
構造設計と直結したCAD/CAMシステムにより、高精度なプレカットが可能です。また、多角形状、曲面形状などの複雑な加工形状にも対応可能です。
5.施工
SE構法の登録施工店ネットワークを活用し、計画に最適な施工店を紹介します。(元請け・建方施工等)
6.非住宅版SE構法構造性能保証
業界初の非住宅木造建築に対応した構造性能保証により安心安全を担保し、中大規模木造建築の計画の実現を後押しします。
↓SE構法へのお問合せ、ご相談は下記よりお願いします。
https://www.ncn-se.co.jp/large/contact/
まとめ
非住宅木造においては、SE構法の構造躯体の強みを活かした構造設計により、コスト減、施工性向上を実現することができます。
SE構法は構造用集成材の中断面部材(柱は120mm角、梁は120mm幅)が標準なため、住宅と同等の部材寸法でスパン8m程度までの空間を構成できるコストパフォーマンスをうまく活用していただければと考えております。
スパンが10mを超える空間は、特注材やトラス、張弦梁などを活用することも可能です。
計画段階からNCNの特建事業部に相談することで、木造建築に関する知見をうまく利用していただき、ファーストプランの段階から構造計画を相談することで、合理的に設計実務を進めることが可能です。
集成材構法として実力・実績のある工法の一つが「耐震構法SE構法」です。SE構法は「木造の構造設計」から「構造躯体材料のプレカット」に至るプロセスを合理化することでワンストップサービスとして実現した木造の工法です。
また構法を問わず、木造の構造設計から構造躯体材料のプレカットに至るスキームづくりに取り組む目的で「株式会社木構造デザイン」が設立されました。構造設計事務所として、「⾮住宅⽊造専⾨の構造設計」、「構造設計と連動したプレカットCADデータの提供」をメイン事業とし、構造設計と⽣産設計を同時に提供することで、設計から加工までのワンストップサービスで木造建築物の普及に貢献する会社です。
株式会社エヌ・シー・エヌ、株式会社木構造デザインへのご相談は無料となっておりますので、お気軽にお問い合わせください。