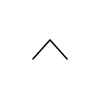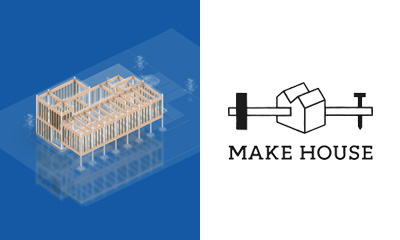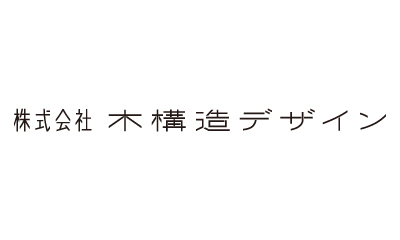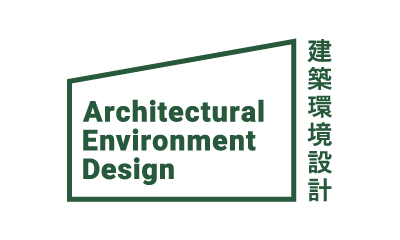【茨城県】中大規模木造の実務ポイントとSE構法の事例まとめ
茨城県では公共施設や商業施設などの非住宅用途でも、条例や指針等を背景に木造化・木質化が進んでいます。
特に公共建築物に県産材を取り入れ、林業支援や環境保全を図る取り組みが目立ちます。
近年は耐火技術や構造技術の向上によって大規模プロジェクトも増え、木の温もりと地域経済の活性化を同時に実現する動きが加速中です。
さらに、補助制度やJAS認定材の活用も広がり、公共のみならず商業ビルやオフィスなど多様な建物で木造化が検討されるケースが増えています。
この記事では茨城県における中大規模木造の実務ポイントとSE構法の事例についてお伝えします。
<このコラムでわかること>
・中大規模木造の普及が進む茨城県の特徴
・茨城県県産木材利用促進条例
・茨城県産木材の利用促進に関する指針
・茨城県における公共建築物等の木材利用
・茨城県の中大規模木造に最適なSE構法の概要
・【茨城県のSE構法事例】笠間市地域交流センターともべ「Tomoa」
・【茨城県のSE構法事例】千波保育園
・SE構法へのお問合せ、ご相談について
・まとめ
中大規模木造の普及が進む茨城県の特徴

茨城県は関東地方の北東部に位置し、豊かな自然環境と首都圏に近い利便性を兼ね備えた地域として、住宅・建築分野でも多様な特徴をもっています。
県西部の筑波研究学園都市(つくば市)を中心とした地域では、計画的な都市整備が行われており、広々とした区画や歩道・自転車道などのインフラが充実していることから、機能性や快適性を重視した住宅開発が進められてきました。
研究機関や大学施設が集積する環境との相乗効果で、高度な技術やデザインを取り入れた先進的な住まいづくりにも注目が集まっています。
一方、県央地域の水戸市などは、江戸時代に徳川御三家の水戸徳川家の城下町として栄えた歴史を背景に、伝統的な建築文化が息づいています。
特に、水戸城や弘道館などは、重厚な木造建築の意匠や庭園文化の特徴を今に伝え、古くからの城下町ならではの趣を感じさせます。
こうした歴史的建造物や景観は、地元の文化遺産として大切に保護・活用されており、近年は観光資源としての魅力向上にも力が注がれています。
また、県南部や鹿行地域(鹿嶋市・神栖市など)は、臨海部に位置する工業地帯や物流拠点が整備されてきた背景もあり、戸建住宅だけでなく、大規模な集合住宅や社宅などが建ち並ぶ地域が点在しています。
海岸線を活かした景観や、広々とした土地を活用した開発が可能であることから、ゆとりのある住環境を望むファミリー層に好まれるエリアとして人気を集めています。
さらに、茨城県は都心からのアクセスが比較的良好で、常磐線や高速道路の整備により東京方面への通勤圏としても発展を遂げてきました。
そのため、ベッドタウンとしての住宅開発が進む一方、自然豊かな里山エリアでは古民家を活用した再生プロジェクトが注目を浴びるなど、多彩な住宅形態が共存しています。
伝統と先端技術の融合、都市的利便性と豊かな自然環境との両立といった多面的な魅力が、茨城県における住宅・建築文化を支えています。
茨城県県産木材利用促進条例

茨城県県産木材利用促進条例は、県産材のさらなる利用促進を目的として、施行されました。
この条例では、県産木材の利用を促進するため、基本理念を定めるとともに、県の責務や関係者の役割を明らかにしています。
茨城県としては、国の補助金や森林湖沼環境税などを活用して施策を推進するとともに、県産木材のより一層の利用促進を図っていく方針です。
この条例で大きな目的として挙げられるのは「地産地消」の推進です。
茨城県産の木材を積極的に利用することで、県内の林業を支援するとともに、森林整備の継続性を確保し、災害防止や景観の保全につなげるという狙いが明確に示されています。
条例では、林業経営者や製材業者、建築業者が一体となり、地域資源を循環利用していく仕組みの構築を重要視しています。
建築実務者としては、設計や施工の段階から県産材を活用するメリットをクライアントへ提案する際に、この条例を根拠として提示しやすくなります。
次に、条例では品質面にも着目しています。
地元の森林で育ったスギやヒノキなどを建築材として活用するためには、適切な管理や品質基準の遵守が不可欠です。
茨城県では、製材や乾燥技術の向上に取り組んでおり、認証制度などを活用しながら品質を担保しやすい環境を整備しています。
建築実務者は、これらの認証材を選択することで施工品質の向上や木材のトレーサビリティ(由来の明確化)を確保できるため、建築主への信頼獲得にもつながります。
また、本条例は「普及・啓発活動」や「連携推進」についても触れています。
県や市町村、関係団体などが連携して情報発信や講習会などを行い、木造建築の技術や事例を広く周知する仕組みを整備することがうたわれています。
建築実務者は、こうした機会を積極的に活用することで、県産材の最新情報や法規制、補助制度について知識をアップデートでき、顧客に対してより具体的な提案が可能になります。
さらに、公共建築物の木質化や木造化の推進も条例の特徴の一つです。
公共建築物に県産材を取り入れることで、県民へのPR効果を高めつつ、木材需要の安定的な確保につなげる狙いがあります。
この取り組みが進むと、木造技術の普及や施工ノウハウの蓄積が広がり、民間建築にも波及効果が期待できます。
建築実務者が公共事業に参画する場合、条例に沿った提案を行うことで受注機会を拡大できるでしょう。
総じて本条例は、茨城県の森林・林業・木材活用の好循環をめざすための基本的な考え方と施策を包括的に示しています。
建築実務者としては、条例が示す県産材の利用促進や品質基準、普及・啓発体制などを理解し、設計・施工において最大限活用することが重要となります。
条例に沿った形で地元木材を取り入れることで、建物の価値向上や施主の満足度向上、さらには地域の林業や経済、環境保全への貢献といった多面的なメリットを実現できるでしょう。
茨城県産木材の利用促進に関する指針

茨城県では、県産木材の利用を促進し、循環型社会の構築と地球温暖化の防止に資するため、「脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律」及び「茨城県県産木材利用促進条例」の規定に基づき、「茨城県産木材の利用促進に関する指針」を策定しています。
県産材を利用する意義として「地産地消」が挙げられます。
茨城県内で生産されるスギやヒノキ、カラマツなどの木材を積極的に活用することで、輸送コストを抑えられるだけでなく、森林管理や製材所など地域の林業関連産業を支援することにつながります。
こうした森林資源の循環利用が、持続可能な林業を育み、次世代への環境保全にも大きく貢献することが意図されています。
また、県産材の品質向上に関する取り組みも重要です。
JAS認定材の普及や、地元の製材業者・流通業者との連携強化を通じて、一定の品質を確保しながら安定供給を目指す方針が示されています。
木造建築物の耐久性や安全性に直結する要素であるため、こうした取り組み状況を把握しておくことで、発注から施工までのプロセスを円滑に進められます。
さらに、木材利用促進のための各種支援制度もあります。
例えば、公共施設における木造化や木質化に対する補助制度の存在、あるいは住宅の新築・改修における助成など、コストを軽減できる施策が用意されている場合があります。
建築実務者としては、これらの制度を顧客に提案しやすくすることで、県産材を用いた建築の魅力をより具体的にアピールできるでしょう。
さらに、木造建築のデザイン面でも、県産材の風合いや特性を活かした設計プランが期待されています。
茨城県産のスギは柔らかな木目や温かみのある色合いが特徴で、内装材や構造材として多様な活用が可能です。
また、気候風土に合った自然素材の採用は、室内環境の向上や健康面でのメリットにもつながると指摘されています。
この指針では、県産木材の利用がもたらす経済的・環境的・文化的効果を強調し、さらにそのための品質管理や支援制度について具体的に示しています。
建築実務者としては、これらの情報を活用し、地元の林業・製材業者と連携しながら品質の高い木造建築を実現しつつ、コスト面やデザイン性、環境配慮など多角的なメリットをクライアントに提案していくことが重要です。
こうした取り組みを進めることで、茨城県内における森林の健全な循環と地域経済の活性化が促進され、木造建築の価値向上にも寄与すると考えられます。
茨城県における公共建築物等の木材利用

公共建築物は、広く国民一般の利用に供するものであることから、木材を用いることにより、木と触れ合い、木の良さを実感する機会を幅広く提供することができます。
このため、建築物木材利用促進基本方針では、公共建築物について、積極的に木造化を促進することとしています。
林野庁の資料「森林・林業白書」によると、茨城県では下記のように木造率が推移しています。
・2017年度:
建築物全体(41.6%)、公共建築物(19.4%)、うち低層の公共建築物(26.7%)
・2019年度:
建築物全体(48.8%)、公共建築物(22.0%)、うち低層の公共建築物(27.4%)
・2021年度:
建築物全体(38.2%)、公共建築物(21.6%)、うち低層の公共建築物(30.2%)
2022年度以降に整備に着手する国の公共建築物については、建築物木材利用促進基本方針に基づき、計画時点においてコストや技術の面で木造化が困難であるものを除き、原則として全て木造化を図ることになっています。
茨城県の中大規模木造に最適なSE構法の概要

耐震構法SE構法(以下、SE構法)は、大規模木造建築物の技術を基に開発された技術です。
SE構法は構造計算された耐震性の高い木造建築を実現する、独自の建築システムです。
SE構法は耐震性の高さ、設計の自由度、コストパフォーマンスの良さ、ワンストップサービス等で高い評価を受けており、さまざまな大規模木造の実績が増えています。
SE構法は、単純に「剛性のある木質フレーム」というだけではなく、さまざまな利点を追求し、大規模木造で求められる大空間・大開口を可能にして、意匠設計者の創造性を活かせる設計の自由度を提供しています。
関連記事:耐震構法SE構法は全棟で立体解析による構造計算を実施
SE構法は「木造の構造設計」と「構造躯体材料のプレカット」そして施工というプロセスを合理化することでワンストップサービスとして実現した木造の工法です。その合理的なシステムが、設計・施工のプロセスにおいて納期や工期の短縮につながります。
関連記事:「ウッドショック等のリスクにSE構法のワンストップサービスが強い理由」
【茨城県のSE構法事例】笠間市地域交流センターともべ「Tomoa」

笠間市地域交流センターともべ「Tomoa」は、茨城県笠間市に建つ公共建築です。
特徴的な局面形状屋根は、周辺地域が建て込んでいるため建物が埋没せず、公共施設として認知しやすい形としたかった点と、遠方の山並みを意識して、曲面形状となっています。
交流ホールの天井は、曲面屋根の形状に合わせ短辺方向に大きな梁を飛ばしており、スパンは13,650㎜とSE構法でも最長クラスの単純梁となっています。

<笠間市地域交流センターともべ「Tomoa」の概要>
・用途:公共施設
・構造:木造(SE構法)
・階数:平屋建
・延床面積:1,442㎡
【茨城県のSE構法事例】千波保育園

千波保育園は、社会福祉法人親愛会が茨城県水戸市で運営する保育園です。
内部においては、屋根形状に合わせた勾配天井を登り梁で構成し、開放感のある大空間を実現しています。

<千波保育園の概要>
・用途:保育園
・構造:木造(SE構法)
・階数:地上2階建
・延床面積:1,367㎡
SE構法へのお問合せ、ご相談について

大規模木造をSE構法で実現するための流れは下記となります。
1.構造設計
SE構法を活用した構造提案を行います。企画段階の無料の構造提案・見積りから、実施設計での伏図・計算書作成、確認申請の指摘対応等を行っております。また、BIMにも対応可能です。
2.概算見積り
SE構法は構造設計と同時に積算・見積りが可能です。そのため躯体費用をリアルタイムで確認可能で、大規模木造の設計において気になる躯体予算を押さえつつ設計を進めることが可能です。
3.調達
物件規模、用途、使用材料を適切に判断して、条件に応じた最短納期で現場にお届けします。また、地域産材の手配にも対応しております。
4.加工
構造設計と直結したCAD/CAMシステムにより、高精度なプレカットが可能です。また、多角形状、曲面形状などの複雑な加工形状にも対応可能です。
5.施工
SE構法の登録施工店ネットワークを活用し、計画に最適な施工店を紹介します。(元請け・建方施工等)
6.非住宅版SE構法構造性能保証
業界初の非住宅木造建築に対応した構造性能保証により安心安全を担保し、中大規模木造建築の計画の実現を後押しします。
↓SE構法へのお問合せ、ご相談は下記よりお願いします。
https://www.ncn-se.co.jp/large/contact/
まとめ
非住宅木造においては、SE構法の構造躯体の強みを活かした構造設計により、コスト減、施工性向上を実現することができます。
SE構法は構造用集成材の中断面部材(柱は120mm角、梁は120mm幅)が標準なため、住宅と同等の部材寸法でスパン8m程度までの空間を構成できるコストパフォーマンスをうまく活用していただければと考えております。
スパンが10mを超える空間は、特注材やトラス、張弦梁などを活用することも可能です。
計画段階からNCNの特建事業部に相談することで、木造建築に関する知見をうまく利用していただき、ファーストプランの段階から構造計画を相談することで、合理的に設計実務を進めることが可能です。
集成材構法として実力・実績のある工法の一つが「耐震構法SE構法」です。SE構法は「木造の構造設計」から「構造躯体材料のプレカット」に至るプロセスを合理化することでワンストップサービスとして実現した木造の工法です。
また構法を問わず、木造の構造設計から構造躯体材料のプレカットに至るスキームづくりに取り組む目的で「株式会社木構造デザイン」が設立されました。構造設計事務所として、「⾮住宅⽊造専⾨の構造設計」、「構造設計と連動したプレカットCADデータの提供」をメイン事業とし、構造設計と⽣産設計を同時に提供することで、設計から加工までのワンストップサービスで木造建築物の普及に貢献する会社です。
株式会社エヌ・シー・エヌ、株式会社木構造デザインへのご相談は無料となっておりますので、お気軽にお問い合わせください。