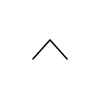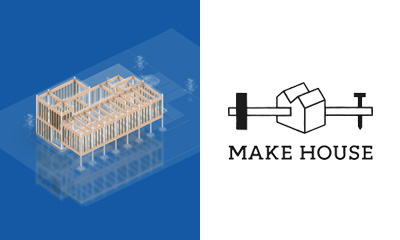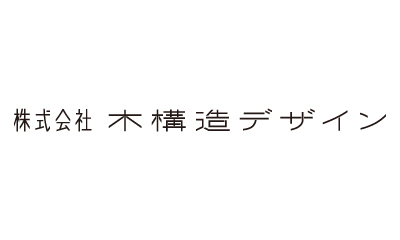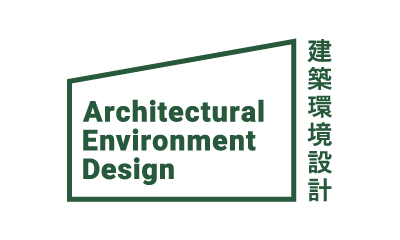【北海道】中大規模木造の実務ポイントとSE構法の事例まとめ
北海道の木造建築では、寒冷地ならではの高い断熱・気密性能の確保が大前提となり、屋根・壁・床等への断熱と気密施工を徹底し、結露対策も入念に行う必要があります。
雪害への対応としては雪荷重を考慮した構造や急勾配屋根、木材の含水率や強度区別の管理、防腐・防蟻処理による耐久性向上も重要です。
寒冷地特性を踏まえた暖房・換気計画と省エネ基準の遵守により、利用者の快適性と建物の長寿命化が両立します。
雪や寒さに適応しつつ、環境性能に優れた中大規模木造を実現することが、北海道ならではの魅力を高めるポイントとなります。
この記事では北海道における中大規模木造の実務ポイントとSE構法の事例についてお伝えします。
<このコラムでわかること>
・中大規模木造の普及が進む北海道の特徴
・北海道地域材利用推進方針
・建築物木材利用促進協定
・北海道における公共建築物等の木材利用
・北海道の中大規模木造に最適なSE構法の概要
・【北海道のSE構法事例】木造4階建共同住宅「LAPEACE(ラピス)」
・SE構法へのお問合せ、ご相談について
・まとめ
中大規模木造の普及が進む北海道の特徴

北海道は日本列島の最北端に位置し、周囲を海に囲まれた冷涼な気候が特徴です。
気候としては亜寒帯湿潤気候から亜寒帯少雨気候まで含まれ、特に冬季にはかなりの低温と多量の積雪が見られます。
この厳しい自然環境に対応するため、住宅・建築に関しては他地域よりも高い断熱性能と気密性、さらには積雪対策が求められます。
具体的には壁や屋根、床下への厚みのある断熱材の使用、二重・三重サッシの採用、隙間を埋める施工技術などが代表的な手法です。
暖房設備も多彩で、床暖房、ヒートポンプ式暖房などが広く普及し、地域や住宅の規模によって最適な熱源システムが選ばれます。
積雪量への対応は、屋根の形状や構造設計にも大きな影響を与えます。
急勾配の屋根は積もった雪が自然に落ちやすいという余裕があり、平坦な部分を少なくすることで雪時間を軽減できます。
融雪槽などを設置して、敷地内や道路の除雪作業を効率化する地域も見られます。
北海道の住宅・建築文化には、明治以降の開拓期に導入された西部式建築技術の影響も色が残っています。
札幌市時計台や函館の教会群、網走や小樽に見られる石造りの倉庫建築など、歴史的価値の高い洋風建築が多く点在しており、観光資源にもなっています。
木材資源が豊富なこともあり、地域産材を活用した木造住宅の普及や地産地消の家づくりが奨励される一方、雪の重み構造による負荷や地震・強風への備えが肝心となります。
これらの課題を解決するために、大学や各種研究機関・企業が連携して建築技術の研究・開発を行い、高断熱・高耐久の住宅技術が進化してきました。
さらに、観光の拡大により、ホテルやリゾート施設、冬のスポーツ施設など大規模な建築物の開発も注目されています。
ニセコや富良野をはじめとしたスキーリゾートでは、海外からの観光客に対応するためのコンドミニアム型宿泊施設や高級ホテルが建設されています。
北海道の住宅・建築は、厳しい寒さや積雪への対応を基本としながら、歴史的で豊かな自然、そして都市計画の特性が複雑に絡み合って形成されています。
北海道地域材利用推進方針

北海道庁が示す「北海道地域材利用推進方針」は、道内の森林資源を持続的に活用し、林業および関連産業の活性化を図るための具体的な方策を提案する方針です。
本方針が強調するのは、公共建築や大規模建築など多様な分野で道産材の需要を喚起し、安定供給的な体制整備を進めていく点です。
寒地で育つ道産材は、樹種によって強度・耐久性や断熱性に優れ、厳しい気候条件にも適応しやすい特徴を持ちます。
特に建築の分野では、新築やリノベーション、公共施設の木造化・木質化など、多面的な利用シーンを想定し、地域材の安定供給の整備や品質管理の強化、設計・施工技術者の育成が求められます。
また、道産材利用の先進事例を積極的に紹介し、設計者や施工者の技術力向上に取り組むことも重要視されています。
例えば、木造の大規模建築や公共施設への適用事例、耐震・耐久性の確保やコストバランスの最適化など、木造化・木質化を普及させるための提言も含まれています。
本方針は道産材活用の意義と具体的な方策を整理し、持続可能な林業と建築文化の発展をめざすガイドラインの役割を担っています。
建築物木材利用促進協定

「北海道地域材利用推進方針」と共に正しく理解しておきたいのが、「建築物木材利用促進協定」です。
「建築物木材利用促進協定」制度は、「脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律」の成立に伴い、建築物における木材利用を促進するために創設されました。
建築主等の事業者は、国又は地方公共団体と、建築物における木材の利用に関する構想や建築物における木材利用の促進に関する構想を盛り込んだ協定を締結することができます。
建築物における木材利用を促進するために、建築主である事業者等と国又は地方公共団体が協定を結び、木材利用に取り組む制度です。
川上と川中の事業者が協定に参画することで、地域材の利用促進にもつながります。
この協定制度は、建築主たる事業者等が国又は地方公共団体と協働・連携して木材の利用に取り組むことで、民間建築物における木材の利用を促進することを目的としています。
協定により、建築主たる事業者等が、建築物木材利用促進構想の実現のために国や地方公共団体と連携して取り組むことで、民間建築物における木材利用(ウッド・チェンジ)を促進し、脱炭素社会・持続可能な社会の実現を目指します。
協定締結のメリットは下記です。
<建築主となる事業者>
・ホームページに公表されることやメディアに取り上げられること等により、当該事業者の社会的認知度が向上するだけでなく、環境意識の高い事業者として、社会的評価も向上します。
・木材利用による炭素固定など環境保全への貢献は、ESG投資など新たな資金獲得につながる可能性があります。
・国や地方公共団体による、財政的な支援を受けられる可能性が高まります。(例:一部予算事業における加点等優先的な措置)
<林業・木材産業事業者>
・信頼関係に基づくサプライチェーンが構築できます。
・事業の見通しができるようになり経営の安定化が図られます。
・林業・木材産業が環境保全に資するという国民理解の醸成が進みます。
<建設事業者>
・信頼関係の構築による安定的な需要の確保が期待できます。
・サプライチェーンの構築による安定的な木材調達ができます。
・ホームページに公表されることやメディアに取り上げられること等により、技術力のアピールができ社会的認知度も向上します。
北海道における公共建築物等の木材利用

公共建築物は、広く国民一般の利用に供するものであることから、木材を用いることにより、木と触れ合い、木の良さを実感する機会を幅広く提供することができます。
このため、建築物木材利用促進基本方針では、公共建築物について、積極的に木造化を促進することとしています。
林野庁の資料「森林・林業白書」によると、北海道では下記のように木造率が推移しています。
・2017年度:
建築物全体(45.5%)、公共建築物(19.0%)、うち低層の公共建築物(35.7%)
・2019年度:
建築物全体(48.5%)、公共建築物(18.2%)、うち低層の公共建築物(34.1%)
・2021年度:
建築物全体(46.7%)、公共建築物(17.8%)、うち低層の公共建築物(32.5%)
2022年度以降に整備に着手する国の公共建築物については、建築物木材利用促進基本方針に基づき、計画時点においてコストや技術の面で木造化が困難であるものを除き、原則として全て木造化を図ることになっています。
北海道の中大規模木造に最適なSE構法の概要

耐震構法SE構法(以下、SE構法)は、大規模木造建築物の技術を基に開発された技術です。
SE構法は構造計算された耐震性の高い木造建築を実現する、独自の建築システムです。
SE構法は耐震性の高さ、設計の自由度、コストパフォーマンスの良さ、ワンストップサービス等で高い評価を受けており、さまざまな大規模木造の実績が増えています。
SE構法は、単純に「剛性のある木質フレーム」というだけではなく、さまざまな利点を追求し、大規模木造で求められる大空間・大開口を可能にして、意匠設計者の創造性を活かせる設計の自由度を提供しています。
関連記事:耐震構法SE構法は全棟で立体解析による構造計算を実施
SE構法は「木造の構造設計」と「構造躯体材料のプレカット」そして施工というプロセスを合理化することでワンストップサービスとして実現した木造の工法です。
その合理的なシステムが、設計・施工のプロセスにおいて納期や工期の短縮につながります。
関連記事:「ウッドショック等のリスクにSE構法のワンストップサービスが強い理由」
【北海道のSE構法事例】木造4階建共同住宅「LAPEACE(ラピス)」

「LAPEACE(ラピス)」は株式会社土屋ホーム様(北海道)で商品開発された木造4階建の共同住宅で、構造躯体としてSE構法が採用されました。
脱炭素社会の実現へ向けて、環境共生住宅として中高層建物を構成する主要構造部材は全て道内産を使用し、道内でプレカットを完結した建物です。
木の快適性、居住性を享受しながらオーナー様、入居者様が共にSDGs達成に貢献できる新たな木造建築物です。

<「LAPEACE(ラピス)」の概要>
・用途:共同住宅
・構造:木造(SE構法)
・階数:4階建
・延床面積:831㎡
関連ページ:SE構法による木造4階建共同住宅の計画・設計まとめ
SE構法へのお問合せ、ご相談について

非住宅木造をSE構法で実現するための流れは下記となります。
1.構造設計
SE構法を活用した構造提案を行います。企画段階の無料の構造提案・見積りから、実施設計での伏図・計算書作成、確認申請の指摘対応等を行っております。また、BIMにも対応可能です。
2.概算見積り
SE構法は構造設計と同時に積算・見積りが可能です。そのため躯体費用をリアルタイムで確認可能で、大規模木造の設計において気になる躯体予算を押さえつつ設計を進めることが可能です。
3.調達
物件規模、用途、使用材料を適切に判断して、条件に応じた最短納期で現場にお届けします。また、地域産材の手配にも対応しております。
4.加工
構造設計と直結したCAD/CAMシステムにより、高精度なプレカットが可能です。また、多角形状、曲面形状などの複雑な加工形状にも対応可能です。
5.施工
SE構法の登録施工店ネットワークを活用し、計画に最適な施工店を紹介します。(元請け・建方施工等)
↓SE構法へのお問合せ、ご相談は下記よりお願いします。
https://www.ncn-se.co.jp/large/contact/
まとめ
非住宅木造においては、SE構法の構造躯体の強みを活かした構造設計により、コスト減、施工性向上を実現することができます。
SE構法は構造用集成材の中断面部材(柱は120mm角、梁は120mm幅)が標準なため、住宅と同等の部材寸法でスパン8m程度までの空間を構成できるコストパフォーマンスをうまく活用していただければと考えております。
スパンが10mを超える空間は、特注材やトラス、張弦梁などを活用することも可能です。
計画段階からNCNの特建事業部に相談することで、木造建築に関する知見をうまく利用していただき、ファーストプランの段階から構造計画を相談することで、合理的に設計実務を進めることが可能です。
集成材構法として実力・実績のある工法の一つが「耐震構法SE構法」です。SE構法は「木造の構造設計」から「構造躯体材料のプレカット」に至るプロセスを合理化することでワンストップサービスとして実現した木造の工法です。
また構法を問わず、木造の構造設計から構造躯体材料のプレカットに至るスキームづくりに取り組む目的で「株式会社木構造デザイン」が設立されました。
構造設計事務所として、「⾮住宅⽊造専⾨の構造設計」、「構造設計と連動したプレカットCADデータの提供」をメイン事業とし、構造設計と⽣産設計を同時に提供することで、設計から加工までのワンストップサービスで木造建築物の普及に貢献する会社です。
株式会社エヌ・シー・エヌ、株式会社木構造デザインへのご相談は無料となっておりますので、お気軽にお問い合わせください。